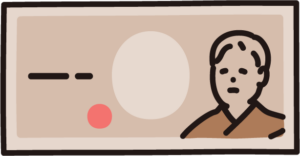フリーランスは国民年金のみの加入なので、厚生年金がある会社員と比べると、将来年金として受け取れる金額がどうしても少なくなってしまいます。なので自分で年金を作っていく・増やしていくことが必要です。そこで今回はフリーランスが年金を増やす選択肢として知っておきたい付加年金に関して解説していきます。
フリーランスが年金を増やせる!「付加年金」とは?
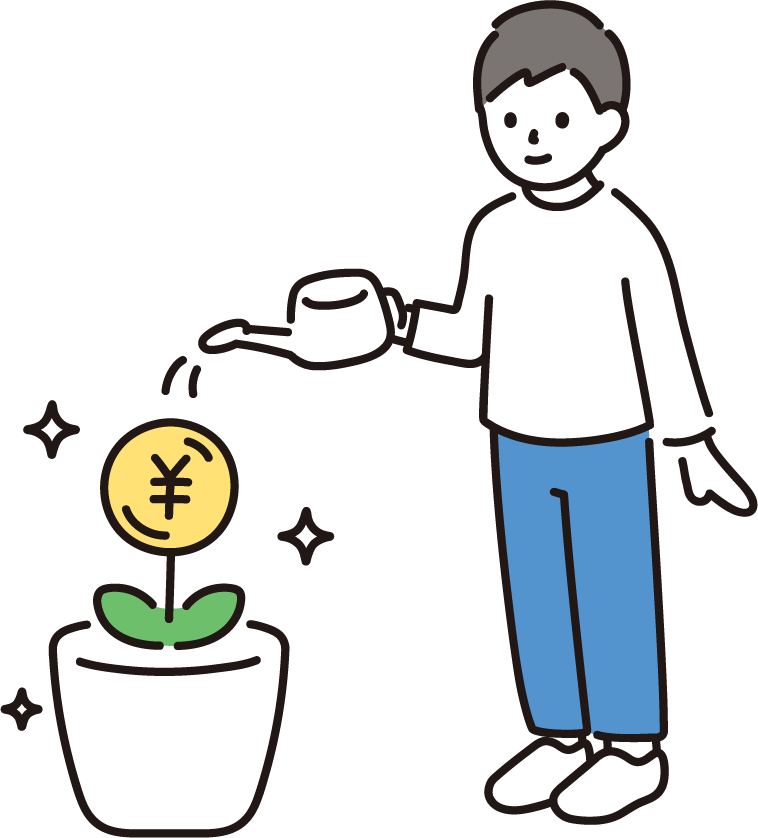
「付加年金」とは国民年金の第1号被保険者(フリーランス・個人事業主など)が利用できる制度で、付加保険料として毎月400円国民年金保険料に上乗せして納めると、将来年金としてもらえるお金を増やすことができます。
将来もらえる年金は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算されます。
例えば付加保険料を35歳から60歳まで25年間支払ったとすると、
- 支払う金額=月400円×12ヵ月×25年間=12万円
- 受け取れる年金額=月200円×12ヵ月×25年間=年間6万円
となるので年金受給の2年間で支払ったお金が回収できます。
付加年金はさかのぼって納付できる?
付加年金は加入前だとさかのぼって納付することはできません。ただ、付加年金をすでに申し込んでいるにもかかわらず納付期限を過ぎてしまった場合は、期限から2年間であればさかのぼって納付することができます。
付加年金は途中でやめられる?
付加年金は途中でやめることが可能です。対象の市区町村役場で「付加保険料納付辞退申出書」を提出すればいつでもやめることができます。やめるまでに払ったお金は将来年金としてしっかり加算されるのでご安心ください!
フリーランスから会社員になった場合、付加年金はどうなる?
フリーランスから会社員になった場合、特別な手続きは必要なく、年金事務所側で付加年金をやめる手続きをしてくれます。再度フリーランスになったり、企業退職後に付加年金へ再加入する場合が再度手続きが必要ですが、もう一度加入することは可能です。やめるまでに払ったお金は将来年金としてしっかり加算されます。
付加年金のメリット
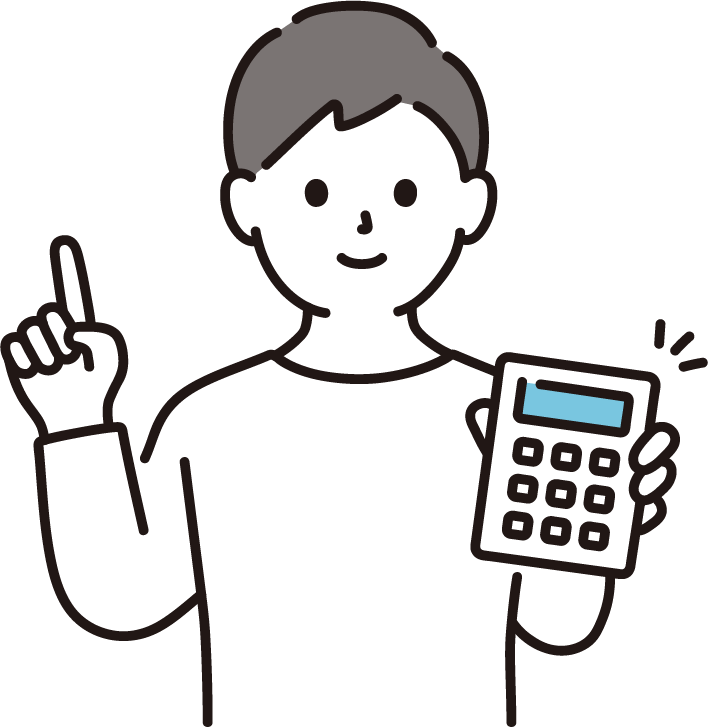
所得税・住民税の節税につながる
付加保険料として払ったものは全額が所得控除の対象となるので、節税効果も期待できます。所得税率は累進課税なので所得が多いければ多いほど節税につながります。
納付した保険料のもとがとりやすい
付加年金は上記で記載のとおり保険料のもとがとりやすいのも大きなメリットです。
例えば付加保険料を35歳から60歳まで25年間支払ったとすると、
- 支払う金額=月400円×12ヵ月×25年間=12万円
- 受け取れる年金額=月200円×12ヵ月×25年間=年間6万円
となるので年金受給の2年間で支払ったお金が回収できます。
老齢基礎年金の繰り下げ受給をすると付加年金も増額される
老齢基礎年金は本来65歳から受け取ることができますが、繰り下げ受給(65歳では受け取りを開始せず、受け取り時期を遅らせる)をすると、65歳から1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額率が加算されます。それにともなって付加年金も同じ倍率で増額されるので、繰り下げ受給をするとより多く年金を受け取ることができます。
付加年金のデメリット

65歳前に亡くなった場合、納付したお金が回収できない
付加年金のデメリットとして挙げられるのが万が一65歳前に亡くなった場合、納付したお金が回収できないこと。死亡した場合でも特に遺族への還付などなく、付加年金としてsk払ったお金は戻ってこないので注意しましょう。
国民年金基金との併用ができない
付加年金と同じくフリーランスが年金を増やす方法として名前が上がる国民年金基金ですが、この2つは併用することができず、どちらか片方しか使用することができません。自分のライフプランを考えてどちらのほうが良いか、しっかり吟味することをおすすめします!
老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると付加年金も減額される
先ほど説明した繰り下げ受給とは逆で老齢基礎年金は繰り上げ受給(65歳よりも前に受け取りを開始する)をすることができます。その場合、65歳から1カ月繰り上げるごとに0.4%ずつ減額されます。老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると付加年金もそれにあわせて減額されてしまうので、この辺りも含めて判断が必要そうです。
物価スライド制に対応していない
付加年金は年金額が確定しているため、受け取り時に物価が大幅に上がっていた場合(インフレの場合)、お金の価値自体が下がっているので、金銭的な価値が目減りしていることがあります。年金に関しては物価に応じて年金支給額を調整する仕組みがありますが付加年金はその仕組みがないのでインフレに弱いということは認識しておきましょう。
付加年金の手続き方法

お住まいの市区町村役場や年金事務所の「保険年金課」へ国民年金付加保険料納付申出書を提出すれば加入ができます。納付開始は申し出をした日の属する月分から開始することができます。
■手続きに必要な持ち物
・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
以上です!
引き続き、よろしくお願いします。